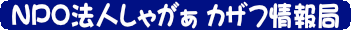Photo Report「イヌワシ祭」
NPO法人しゃがぁ会報vol.47(2009年12月発行より本文のみ転載)

イヌワシ祭とは、 カザフ民族に、 古くから伝わってきた祭では“ない”。 今回、私が取材したイヌワシ祭はバヤンウルギー県に本社を置くブルーウルフ社がちょうど今から10年前に始めた新しい祭だ。ブルーウルフ社は今ではモンゴル4大旅行社の一つに数えられるような旅行社であるが、社長のカナットは、「カザフ文化を保護、維持、発展させていくこと 」を目的として、この祭を始めたのだという。ブルーウルフ社は、カナットが英語が堪能なことも手伝って、古くより欧米からの観光客を多く受け入れてきた。今では、中国、カザフスタン、 ロシアなどの旅行社と広く提携を結び、アルタイ山脈地域を一大観光地とするべく活動をしている。彼が祭を始めた当時より、彼とは別の組織もまた同様のイヌワシ祭(ブルグディンバヤルと現地では言う) を同期日に行うようになり現在に至る。例年、10月の第一週目に開催されてきたのだが、今年から、9月半ば過ぎ開催となり、かつ祭の回数も増えたという。イヌワシ匠たちは、参加すると参加賞金がもらえ、よい成績を収めれば、 さらに賞金ももらえるので、できるだけたくさんの祭に出たいと考えている。
そのため、同時期日の開催は当事者の間でも不評だったらしい。また、海外からの旅行客からのチケット収入が祭の運営費となっており、同期日開催で収益がおちこみ、結果、運営資金不足となり、開催前に約束された報酬を得られないなど問題が起きたこともあるという。従って、今回のように期日がずれ、祭の回数が増えるのはとても喜ばしいことなのだ。ところが、モンゴル国内線は10月に入ると、特にバヤンウルギー行きのフライトは減ってしまう。ウランバートルからウルギーへ非常に行きにくくなるのだ。たくさんの外国人を招致したい主催側には、最大のボトルネックとなっていたのだ。「モンゴル中央部は俺たちカザフの発展を望まないんだよ。 」などと言うカザフ人もいる。「中国新疆ウイグルからホブドへの就航やカザフスタンやアルタイからウルギーの飛行機乗り入れとか、中国側、ロシア側、カザフスタン側などすごい乗り気なのに、モンゴル中央が邪魔をするんだよ。」と聞いたこともある。もしも、これらのルートが開かれたなら、西モンゴルのホブド、ウルギーに経済中心地が作られ、ウランバートルへの一極集中によって引き起こされる問題も緩和されるだろう。旅行者にしてもアプローチルートが増えるのはとても楽しいので歓迎するところだ。
 |
 |
さて、イヌワシ祭に話を戻そう。とにかく、今年は観光客招致を最大の目標として、祭を10月開催としたらしい。結果、祭の規模も様々だというが、あちらこちらで祭が解されるようになった。そんな中でも、ブルーウルフ社とサグサイ郡が共催で行う祭は、中でも 1,2を争うものらしい。実は、祭を去年まで10月始めに開催していたのには訳がある。以前、 しゃがぁ本誌上でも紹介したが、イヌワシを使った狩りは、基本的に秋半ば過ぎから冬にかけての時期である。毛皮を取ることが目的の狩りであるから、獲物である狐などの毛皮がきれいになる時期に行われるのだ。従って春から秋にかけての時期は、イヌワシの訓練期間となっている。
イヌワシ匠の話によれば訓練期間中には、ワシに肉を与える機会が多く、狩りの時期になるとあまり与えなくなるのだそうだ。つまり、夏が終わってすぐの時期などだと、腹一杯のイヌワシは、狩りを行わないのだという。つまり飛ばないと。祭の時期としては、10月も遅くなってからの方が本当はいいのだという。
ただ見物客としては、あまり寒くなってから野外で長時間の見物はできないので、人をたくさん集めたい主催者としてはジレンマを抱えていることだろう。
そんな中での9月開催のイヌワシ祭だったが、多くが予想したように、やはりイヌワシ狩りのデモンストレーションは少々困難があったようだ。
 |
 |
競技は馬上からワシを呼び寄せる競技、毛皮を引っ張ってそれを捕まえさせる競技が行われ、どちらもが飼い主が呼び始めてから降り立つまでのタイムトライヤルだが、飛び立つなり、 全く違うところへと飛んで行ってしまうワシが少なくなかった。また、ある程度離れたところに降り立つとはいえ、周囲にたくさんの見物客がいるため、降りかけたのに、そのまま飛び去ってしまったりするイヌワシも多かった。 私はファインダーをのぞきながら、 馬上の飼い主を追いつづけ、イヌワシがフレームに入ってくるのを待つのだが、いつまで経ってもイヌワシがやってこないということも多かった。フレームの外側を飛び去っていったり、さっさと着陸してしまって歩いてくるイヌワシはとてもかわいかったのだが、とても格好良く決めている飼い主たちがとても絵になる分、両者の対比がとてもユーモラスだった。現地の観客たちも、「やっぱり9月じゃ、まだはやいかねぇ」などと口々に言っていた。 あえて、どうして?と訊ねると、やはり
「だって、ワシのやつ、腹一杯だろ。」という答えだった。
 |
 |
カザフ民族、カザフ文化などと関わり初めて、かれこれ5年ちょっとになるのだが、彼らをみていて、いつも思うのが、「おしゃれな人たちだなぁ」ということだ。毛皮の外套のパッチワークの紺み合わせ、狐の足の色違いを組み合わせて作る帽子、帽子の上につけられた羽、襟に刺繍の施された外套、膝下に刺繍の施されたズボン…。どれもこれも、普通に着ているのがとても粋なのだ。今回、カナットが、私に刺繍入りの外套をプレゼントしてくれた。黒地に白で、襟、袖口、裾、背中に刺繍が入っている。会場ではこれを来てカメラパックをぶら下げていたのだが、気がついたことが一つある。この外套にはポケットがない。羽織って、ベルトで腰をしめると、ズボンのポケットも使いにく くなってしまう。モンゴル服だと、右胸上部のボタンで留めて、 帯を巻いた後、 胸前部分にポケッ
トスペースができるので、便利なのだが、前合わせの、カザフガウンはそれができない。で、使われるのが、たすき掛けでぶらさげるカバンやベルトからぶらさげるポーチだ。 もちろん、これにも色鮮やかな刺繍が入っている。施されている。それに、黒や青、濃い緑のガウンに赤を基調とした刺繍は実に、美しい。どこもかしこも刺繍だらけというのは、とても色が派手で、模様も多すぎて、落ち着かないような気がするが、そんなことはない。むしろ沢山の刺繍に囲まれ、自分もまた刺繍の一部になってしまったように思える。そして、少々深読みなのかもしれないが、すべての模様に意味があると思うと、その一部になった自分にも意味があるのだとも思えるのだ。一見何もないかのような、 大草原やアルタイ山麓の荒野なのだが、ここに立ち、そこに住む彼らに近づいていけば行くほどに、すべてのモノに意味があり、価値があると思わせてくれ、自分の意味を考えることができる。何もないからこそ、人は人であろうとするのかもしれない。何もないようで、必要十分にすべてのものがあるのかもしれない。こういう所に来ると、無駄かもしれない色々なモノに囲まれる生活を、いつも反省させられる。
さて、 祭の話。
 |
 |
イヌワシとイヌワシ匠がメインの祭だが、カザフ文化の祭典という演出もされていた。
アイテスという即興歌による歌合戦や、 クズコアルという遊びも実に興味深いものだった。 クズコアルとは、男女二人で組になり、女性は男性をムチでたたきながら追いたて、男性はそれからおもしろおかしな演出をして逃げるというものだ„ 男性が最初にキスをするのだそうだ。 それが求婚の合図ということで、そして、 女性がそれを受け入れたなら、相手を追い立てるというのがカザフの習慣にあったのだという。かつては逃げる男性と追う女性が走りまわることで、 二人がこれから夫婦となることを周知していたらしい。その様子をおもしろく見せることとして、競技化したようだ。 ただ、このことは今後、もう少し詳しく識者などに確かめたいと思っている。
 |
 |
他に、 ヤギを奪い合うククパルというのが行われた。これは祭の最初にヤギを一頭殺し、そのヤギを騎乗した二人が奪い合い、勝ち抜いていく競技だ。地面に横たわっている30〜40kgはあるヤギを馬上からすくい上げるところから競技は始まる。 先に持ち上げた方が、まずは自分が持ちやすいようにヤギを抱える。そして、 もう片方の足を相手に握らせる。そうしてから、ウマを上手に操って奪い合いを始めるのだ。
また、テンゲイルウという競技も行われた。地面に置かれた薄い平らなコイン状のものを馬上から拾い上げる競技だ。ウマの足を止めてはならない。順々に拾い上げていき、最多数を拾った人が勝ち抜いていく。コインの間隔は試合が進むにつれ狭くなっていき、拾い上げるのは徐々に難しくなっていく。
ククパルにせよ、テンゲイルウにせよ、高度な乗馬技術が要求される。勇壮なカザフ男としての技量を多くの人々に誇示する格好の場なのだ。
 |
 |
 |
さて、 一つ、気になったことがあった。ブルーウルフ社主催ということで、外国人は皆、ツーリストキャンプをベースに会場に通い、各グループそれぞれに運転手付き卓と、コックさんが付くのだ。正直、私としては面白くない。というのも、このコックさん(人としてはとても良い人だったが)、作る料理はすべて外国人向け料理なのだ。カザフのお茶も力ザフの食べ物も一切出てこない。カナッ卜日く、「欧米のお客のほとんどが、こういうのをリクエストするんだ」とのこと 。当然、私は、「カザフ茶を出せ一!カザフバターを出せ一!カズ(カザフの保存用馬肉)を出せ一!」とわがままを言って、カザフ食を出させたのだが、周りからは怪訝な顔をされた。カザフ文化を知らしめたい人々と、興味を持ってやっては来たが、自分の背負ってきた文化から外に出られない人々がいるようだ。
カザフの土地で、 カザフに触れる。わざわざ遠くからやってきたのだから、当然のことだ。モンゴル国バヤンウルギー県、ここにはいままでカザフを背負い、そして、これらを担う、 カザフの人々が生き生きと暮らしていた。